こちらの記事で投資信託の定期売却について紹介しました。
インデックス投資は「適切に分散された低コストのファンドを可能な限り長期に保有する」ことによって利益を得ようとします。
私を含めてインデックス投資家は、投資の始め方と継続の仕方をテーマにすることはありますが、利益を得た後のこと、すなわち出口戦略についてあまり考えて来なかったと思います。
買って保有しているインデックス・ファンドについては、いつかは売却して現金化する時が来ます。
今回は、インデックス投資の終わらせ方に焦点を当てて、実際の数字でシミュレーションを行ってみました。
過去20年間を例にとって考えてみます。
どんな想定?
オルカンやスリムSP500といった超優良投資信託は、20年前には存在していません。
ですので今回も楽天証券の投信スーパーサーチで「インデックス、グローバル、株式、運用期間20年以上」で検索してみました。

7件ヒットです。
この中で管理費用(信託報酬)が最安値の「インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド」をピックアップ。
個人年金保険の記事でも登場いただいた、ベテランインデックスファンドです。
この投資信託を65歳時点で新NISAで1800万円保有していたとします。
2003年から2023年までの20年間に、毎年年初に決まった方法で売却しました。
65歳から85歳のまさに老後の20年間において、資産はどうなったのか?
期間指定
まず、決められた期間で資産を必ず使い切る、「期間指定」の場合です。
この「期間指定」は、私が資産を取り崩す際に使おうと思っている売却方法です。
我が家のように後に多額の資産を残す必要のない人には、候補になる方法だと思います。
期間指定で売却した結果は?


表にはありませんが2023年1月に売却した結果、残金は47円となりました。
まさに使い切りw
上の表を見ると毎年の売却口数が一定になっています。
65歳時点での口数を指定した期間で割っているので、口数は一定になります。
ただし一口当たりの基準価額が変動するので、売却金額は変動しています。
期間指定の結果を見て
まず目に付くのは、リーマンショック時(2009年:71歳)の減少額です。
リーマンショックによって基準価格は半減し(13800から7000に大暴落)、その結果売却額も半減しています。
しかし、それでも毎月65000円を維持しています。
その後2013年以降は上昇を続け、2023年(85歳)では毎月33万円になっています。
この間の総売却額は約4000万円であり、当初の1800万円の約2倍となりました。
これが資産運用しながら取り崩しを行う、一番のメリットです。
しかしながら後半にかけて、特に80歳以上になって毎月20~30万円を取り崩すことになり、バランスの悪い結果となりました。

85歳で33万円もあっても、、、何に使いましょうか??w
金額指定
次に毎月売却する金額を固定する、「金額指定」の場合はどうでしょう?
この方法は、年金等の他に必要な金額を指定できるメリットがある反面、相場の状況によっては想定よりも早く資産が無くなってしまう危険性があります。
毎月10万円売却時


毎月10万円(年120万円)売却したとしても、85歳になっても資産は無くなっていません。
無くなるどころか1500万円を維持しています。
もうちょっと売却額を増やしてみます。
毎月12万円に増やしてみると


毎月12万円(年144万円)売却すると、85歳時点で120万円の残り。
総額で約3000万円を売却しており、なかなか良い感じです。
毎月15万円なら?


毎月15万円(年180万円)売却すると、78歳時点で資産がマイナスになりました。
ちょっとやりすぎましたね。
金額指定の結果を見て
2003年から2023年の間は、100年に1度と言われたリーマンショックを含んでいます。
確かに2009年での資産の減少を見ると、毎月定額を売却することに躊躇するかもしれません。
しかし、結果から振り返ってみると毎月12万円というかなりの金額を売却し続けたとしても、資産がなくなることはありませんでした。
株価の暴落に(心理的に)耐えられるなら、生活に必要な金額を指定できる「金額指定」での売却は、有力な出口戦略になりそうです。

老後は相場を見ない!これが正解かも?!
定率指定
最後に「定率指定」を確認してみます。
この「定率指定」はいわゆる「4%ルール」という、インデックス投資家によく知られた出口戦略を採用できる方法になります。
定率指定の場合には、毎月の売却額も売却の期間も全て変動します。
相場の状況によっては、予想外に少ない金額や、短い期間になってしまう可能性があり注意が必要です。
4%で定率指定の場合


毎年4%で売却した結果、85歳時点で約3600万円まで資産が増加しています。
その間、約2000万円を取り崩せています。
しかし2009年(71歳)と2012年(74歳)は毎月4万円台の売却となり、老後2000万円問題の毎月5万円をクリアーできませんでした。
もう少し率を上げてみます。
倍の8%にしてみると


毎年8%で売却した結果、85歳時点で約1400万円資産が残りました。
総売却額は2600万円であり、毎月の売却額も5万円を下回ることはありませんでした。
いっそのこと15%まで上げてみた


毎年15%で売却した結果、85歳時点での残金が約300万円となりました。
総売却額は2600万円を下回っており、8%で売却した時よりも少なくなってしまいました。
毎月の売却額も、特に後半は5万円を下回ることが多くなり、やはり15%はやりすぎでしょうか?
定率指定の結果を見て
この期間のMSCI コクサイ・インデックスは、年率約10%となっています。
この10%を下回る率で売却を続けていれば、資産は維持できたことになります。
特に2009年のリーマンショック時の下落を、4~8%の売却率では挽回できましたが、15%ではまったく挽回できず、その結果が後半の金額減少につながったようです。
毎月の売却金額が一定しない「定率指定」はなかなか老後の生活場面では使いにくいと感じましたが、みなさんはどうでしょうか?

使い切るぞ!の期間指定とは違い、資産を残すぞ!の定率は相場に心を乱されそうです。
定期売却をやってみて

現実に存在する実際の商品を使って、定期売却のバックテストをやってみました。
結果としては、老後の生活のために資産運用をするのであれば、毎月固定の金額が入金される「金額指定」が有力な出口戦略になると感じました。
実際リーマンショック級の大暴落がくれば、売却額を減額するでしょうし、そうすれば資産寿命はもっと延びると思います。
一つ言えることは、1800万円の資産を運用すれば、老後問題なんて無いに等しいということ。
新NISAを埋めるモチベーションも高まります。
最後に
今回は投資信託の出口戦略として、定期売却を実際にやってみました。
今回やったバックテストは、過去に起こった一回切りの現象に当てはめてみただけです。
当然今後の未来は、これとは違った結果となるでしょう。
しかし、私たちは世界経済が長期に渡って成長し、株価が(結果として)右肩上がりに上昇すると思うから投資するわけです。
私としては、過去20年間がそうであったように、これからの20年間もルール通りに淡々と投資を続けていけば、素晴らしい結果になると思っています。
なので「適切に分散され低コストなオルカンを買って可能な限り長期に保有する」というインデックス投資を淡々と継続していきます。

老後になるまでまだ20年以上。いくらまで資産が増えるかな~
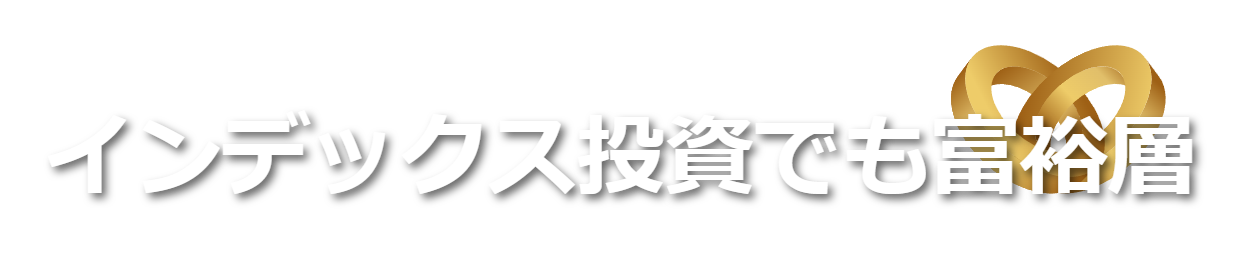


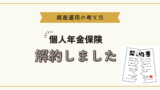



コメント